子どもの日にあげる、「鯉のぼり」
男の子の成長を願ってあげる鯉のぼりですが、いったい子供が何歳になるまであげるものなのでしょうか?
由来と合わせて知ると、「飾るべき年」が見えてきますよ。
鯉のぼりは何歳までだす?
まず、鯉のぼりは何歳まで飾ってよいのか、という決まりのようなものはありません。いつまででも飾っていいのです。
ただ、鯉のぼりは外に出すものですし、あまり一般とかけ離れすぎていて、恥をかくのは嫌ですよね。
ほとんどの家は子供が嫌がり始めたら、やめる、という家が多いようです。
こどもの日は鯉のぼりのほかにも兜や五月人形を飾ったりしますよね。それらは家の中ですし、人形ということであまり恥ずかしがるということはなさそうですが、やはり、男の子も年頃となれば、「恥ずかしい」などと気にしてしまう場合が多いようですね。
大体、その年齢というのが、中学生にあがるころや、小学校中学年になる7,8歳のころが多いようですね。
決まりがあるものではありませんので、少し寂しいような気もしますが、子供が嫌がったら出さなくてもいいのかもしれませんね。
子どもの日の鯉のぼりの由来は?
近頃の一般的には、7,8歳、または中学生くらいという家庭が多いとお話しをしました。
なので地域の決まりや風習がなければ、「子供が嫌がるまで」でOKとお話ししました。
では次は由来から考えてみましょう。
5/5の端午の節句という行事自体は奈良時代から行われているものです。
ですが、まだこのときは5月5日は子供の日という男の子の成長を祝ったり、願ったりする日ではありませんでした。
奈良時代や平安時代では、子供の日ではなく「約歳を避けるための行事」でした。
このころの宮廷では、軒に菖蒲やよもぎを飾ったりしていました。
そして、鎌倉時代になります。
鎌倉時代は武家の時代です。武家では「菖蒲」と「尚武」をかけて、5月5日をとても大切にしました。
江戸時代では5月5日は、幕府の重要な式典の日になりました。大名たちは、江戸城へ行き、将軍にお祝いを告げます。刀や兜などを飾り、盛大にこの日をお祝いするようになったのです。
「鯉のぼり」が生まれたのは、そんな江戸時代のことです。
庶民のアイデアで鯉のぼりが生まれたのです。
「鯉のぼり」の由来はご存知の方も多いはず。
中国に伝わる登竜門の伝説ですね。
黄河中流にある竜門を魚たちがのぼあろうとする中、みんなが失敗していきます。ですが、鯉だけは上るくとができ、竜になるという伝説です。
このことから、我が子も、健康に育ち、立派に出世してほしいという願いを込めたのが「鯉のぼり」です。
江戸時代の鯉のぼりはまだ、和紙に鯉の絵を描いた簡単なものでしたが、大正時代には、ほとんど今とおなじような破れない綿でできた鯉のぼりが生まれました。
江戸時代の庶民の間で、5月5日にお祝いに武具を飾るのではなく、鯉のぼりを飾るようになったというのが始まりです。
男児の健康や出世を願ってあげる鯉のぼり。
昔は、男の子の成人といえば15歳。
立派な大人となった男の子に鯉のぼりをあげるのはおかしな話なので、せいぜい15歳までというのが、由来から考える、上限ではないでしょうか?
まとめ
いかがでしたでしょうか?
鯉のぼりをいつまで上げるかは個人個人の自由で決まりはありません。
基本的には子供が嫌がるまで上げるのが一般的です。
また子供がいつまでもいやがらなくても、15歳までが限度と考えたほうがよさそうですね。
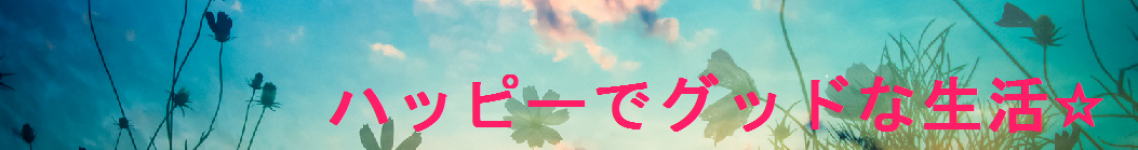



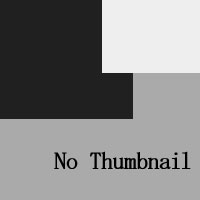










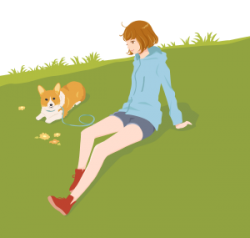
 TOP
TOP